芝大門 いまづ クリニックからのお知らせ



芝大門 いまづ クリニックからのお知らせ
2016(平成28)年2月15日(月)BSジャパン「日経モーニングプラス」7:30~7:50
「急増!インフルエンザの治療法」に、生出演させていただきます。
2016(平成28)年2月15日(月)午前の診療を休診させていただきます。
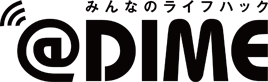
全国の100歳以上の高齢者の人数が6万人を超え、日本の長寿人口は驚くほど増えている。100歳まで健康に生きられる長寿法はあるのか。あるとしたらそれはいったいどんなものなのか。専門家の意見を聞きながら考えてみよう。(取材・文/大場真代 編集協力/プレスラボ)
6万1568人――。
この人数が何を示すか、おわかりになるだろうか。厚労省の昨年の調査で、全国の100歳以上の高齢者が6万1568人となり、過去最多となったのだ。
100歳以上の人口は1971年(339人)から45年連続で過去最多を更新しているが、6万人を超えたのは今回が初。老人福祉法が制定された1963年(昭和38年)には、その数は全国で153人だったが、1981年(昭和56年)に1000人を超え、1998年(平成10年)には1万人を超えた。白寿を超えることは、昔よりも珍しいことではなくなってきている。
そこで気になるのが、100歳を超えるまで元気な人たちは、いったいどんな健康法を行なっているのか、ということだ。必ずしも全ての人が「100歳まで生きたい」と思っているわけではないだろうが、前述のような報道を見て、「自分も100歳まで生きることができるのだろうか」と考えた人は少なくないだろう。
100歳まで生きられる長寿法はあるのか、あるとしたらそれはいったいどんなものなのか、調査・考察してみよう。
「過去のデータで、確実な記録がある史上最高齢は、フランス人女性(故人)の122歳164日です。日本人では現在、今年116歳になる女性が最高齢です。こうしたことから考えると、現時点での寿命の限界は110~115歳くらいでしょう」
こう話すのは『115歳が見えてくる“ちょい足し”健康法』(ワニブックス)などの著書がある、芝大門いまづクリニックの院長・今津嘉宏医師だ。
しかし、100歳が珍しくなくなったとはいえ、いくら長生きをしても寝たきりのままでは幸せな老後とは言えない。平均寿命が80歳の今、その後の30年間を寝たきりの生活ではなく、人生を楽しむ時間にあてるためにも、「健康のまま寿命を全うできるか」が問題になってくる。いわば「健康寿命」だ。
実際に、厚労省が発表した100歳以上の高齢者調査を見ても、ゴルフをやったり歌を歌ったりするなど趣味を楽しんでいたり、自分で身の回りのことをすべて行っていたりと、元気に過ごしている人が多いことがわかる。中には、100歳超で100メートル走の世界記録を持つ人さえいる。このような人たちの暮らしを見ると、健康のまま寿命を全うすることは不可能ではないことがわかってくる。
とはいえ、「そういう人は遺伝的に長生きなのでは?」と思う人も少なくないだろう。癌にかかる人は日本人の2人に1人、今後ますますその数は増えてくると言われるなか、健康で長生きするのはとても難しいことのように思える。しかし、今津医師は言う。
「昔は長生きする人は遺伝が関係していると言われていましたが、あまり関係ないことが最近の研究でわかってきました。厚労省の統計でわかった長寿の方の共通点は、精神的に明るく、そして規則正しい生活をしていることだったのです」
一般的に「健康に気をつける」というと、お酒やたばこを控えるのはもちろんのこと、ファストフードや西洋的な食事も控える、定期的な運動をする、ストレスを極力減らす、といったことを想像しがちだ。しかし長寿の人は、実は特別なことは何もしていないことが多いという。
「お酒やたばこが大好きな人もいますし、お肉が好きで毎日のように食べている人もいます。実際、現代の生活の中で『健康リスク』と言われていることを一切除外するのは難しいでしょう。特に働き盛りの40代くらいであれば、ストレスはないほうがおかしいくらいです。自分自身の普段の生活の中で無理のない方法を取り入れていくことが、長生きのためには大切なのです」(今津医師)
では具体的にどのような方法が、心身ともに健康に動ける寿命である「健康寿命」を延ばすことができるのか、今津医師は「上体温」「食事」「睡眠」の3つがカギになると話す。
順番に、まず「上体温」から説明していこう。「上体温」とは、端的に言って体温を上げること。今津医師が説明する。
「私が小さい頃、おばあちゃんから『身体を冷やしちゃダメだよ、風邪をひくし、病気になるよ』とよく注意されました。シンプルな意見ですが、身体が冷えると実際に病気になりやすいことがわかっています。逆に、体温を上げることで、87.796%の病気は防ぐことができます。 体温を上げることで防げる病気というのは、糖尿病や高脂血症、高血圧症、痛風、心臓病、肥満、認知症、脳血管疾患、うつ病、がんなどの生活習慣病。つまり冷えは万病のもと。身体を常に温める生活習慣を送ることで多くの病気が防げます」
「身体が冷えるにつれ、脳神経の活動が休息状態になることがわかっています。つまり、これは身体が冷えると脳自体が働くなって、命の危険に晒されるということ。また、身体を冷やすことで、身体の細胞の働きも低下し、免疫力も低下します。冬に風邪を引きやすくなるのもそのためです。普段から身体を温めるような食材を積極的に摂るなど、自分に合った体温を上げる方法を身につけてみましょう」
具体的にどのくらい体温を上げるか、それは平熱が35度の人は35.1度、36度なら36.1度というように、平熱を基準に体温を上げればよいそうだ。
そのために行うことは2つある。
(1)朝起きて飲むものに気をつけること
人間の身体の60~70%は水分でできているため、寝ている間に失われた水分を補給するのは大事だが、それを冷たいものでなく温かいものにするのがいいという。
「朝起きたてで冷たいものを飲むと、胃腸を冷やし、消化能力を下げてしまいます。冷たい水を飲むのを健康法にしている人は、その前に運動して身体を温めるなど、必ず何か他の習慣がセットになっているはずです」(今津医師)
人間の体温は起床時が最も低く、だいたい深部体温は37度ほど。常温の水であっても冬ならそれ以下になっているので、少し温めてから飲むのがよいだろう。
(2)身体を温める食材を摂る
身体を温める食材というと、唐辛子などの辛いものを思い浮かべるかもしれないが、唐辛子には発汗作用があるため、結局身体を冷やしてしまうことになる。激辛料理が南国で発達してきたのもそのためだ。身体を温める食品はネギ、ショウガ、にんにくの3つ。
「アメリカ国立がん研究所が、長年の疫学的研究データに基づいたがん予防に効果のある食品を『デザイナーズフードピラミッド』として1990年に発表したものにも、がん予防に最も効果のある食材の中にショウガとにんにくが入っています。また、寒い季節や寒い地方で採れる食品、特に根菜などは身体を温める作用があります」
次に「食事」についてはどうだろう。
身体を温める食材を摂る以外では、何が重要か。それは「過ぎたるは及ばざるがごとし」。どんなものでも摂りすぎに注意する必要があるという。
「身体にいい食品に関して一番有名な研究で、カボチャやにんじんに含まれる『β-カロテン』というビタミンの実験があります。試験管やネズミの研究では、β-カロテンを摂ると、がんが発生しなくなるというデータが出たのですが、これを受けてβ-カロテンを3倍量飲ませた治験を行うと、肺がんの発生率が3倍に増えたというのです。よかれと思って摂取しているものも、このように摂りすぎるとかえって病気を引き起こしてしまうこともあるのです」(今津医師)
健康にいいと言われているサプリメントやトクホなども同様。これらはあくまでも「食品」。どんなに摂っても病気を治すことはできないし、同じものを食べ過ぎれば病気になる確率も高くなってしまう。だからこそ、どれか1つのものを摂るよりも、バランス良く、自分に合った食生活を心がけることが重要なのだ。
そして、健康でいるために最も重要なのが「睡眠」だ。日本人の平均睡眠時間は7~8時間だが、長く寝れば寝るほどいいかと言えば、そうでもないのだという。睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」「中途覚醒」の3種類がある。レム睡眠は、身体は眠っているのに脳は起きている状態、つまり夢を見たり寝返りを打ったりしている状態を言い、ノンレム睡眠は深い睡眠で脳も休息している状態、中途覚醒は途中で眼が覚めてしまうことだ。この3つを組み合わせて、私たちは睡眠を取っている。
「健康寿命を延ばすには、ノンレム睡眠を増やす必要があります。ノンレム睡眠には、心と体を休めること、記憶することと忘れること、成長ホルモンを分泌する、免疫力を上げるという4つの役割があります。とはいえ、睡眠時間が長すぎるのもNG。平均的な睡眠時間7~8時間の人に比べると、5時間未満の人は糖尿病になる確率が2倍以上になり、9時間以上だと1.8倍になるというデータもあるのです」(今津医師)
休みの日は、疲れを取ろうとつい「寝だめ」をしてしまいたくなるが、睡眠時間を長く取っても、健康寿命を延ばすノンレム睡眠の時間が増えるのではなく、ノンレム睡眠と中途覚醒が増えているだけだ。つまり「長い睡眠=よい睡眠」ではないため、長時間の睡眠でも糖尿病になる確率が上がってしまうのだという。
「つまり、睡眠は長さではなく質。たとえ1時間しか寝られない日があってもいいのです。勉強したことを暗記するためなのか、それとも嫌なことを忘れるのか、身体を休息させるのか、その時々で寝る目的が果たせれば、質のよい睡眠がとれたと言っていいでしょう」(今津医師)
そのために大切なのが、起きる時間を決めること。人間の身体は太陽の光を浴びると覚醒のスイッチが入る。さらに朝食を取ることで、身体中の睡眠スイッチがオフになり、身体のリズムも整ってくるという。
「健康にとっては食事も大切ですが、睡眠はもっと大切です。運動ができない環境や、お酒を断ることができない環境にあるなら、睡眠に投資することを考えたほうがいいです。寝具を整えるだけで、睡眠の質はかなり変わってくると思います」
と、ここまで「上体温」「食事」「睡眠」と健康に欠かせない三要素について解説してきたが、最後に大事なのは三日坊主にならない習慣を身につけることだと、今津医師は言う。
「嫌いなものを食べたり、ライフスタイルに合わないことを実践したりして三日坊主になるよりも、自分に合ったものを取り入れて習慣にできる方法を少しずつ増やすほうが、長生きできます。長寿の方たちが特別なことをしていないというのは、普段の生活の中に健康になる要素がたくさん含まれているから。115歳まで元気に長生きするためには、自分にとって面倒だと思うことではなく、無理なく取り入れられる方法を見つけること。無理のない範囲の健康法を身につけ人生をエンジョイすれば、115歳まで生きることも不可能ではありませんよ」
自分に合った健康法を無理なく楽しく続けること。どうやらこのあたりにヒントがありそうだ。もちろん、ここで紹介した長寿法を実践すれば必ず100歳まで生きられとは言い切れないが、健康が気になる向きは参考にしてみてもいい。また、身近に長寿な人がいたら、そのライフスタイルを聞いてみるのも面白いかもしれない。
2016(平成28)年2月8日(月)BSジャパン「日経モーニングプラス」7:30〜7:50
『健康情報 Gooday』に、「急増する!インフルエンザの対処法」で生出演させていただきます。
2016(平成28)年2月8日(月)午前の診療時間を
午前10時から とさせていただきます。
2016(平成28)年2月3日(水)テレビ東京 午後6時57分〜
「ソレダメ!」に出演させていただきます。
2016(平成28)年2月1日(月)フジテレビ「バイキング」
出演させていただきました。ありがとうございました。
ひるたつ〜医者が薦める冬の2大健康食材
2月が旬!大根&長ネギ 名医イチオシ健康レシピ
東京大学 医学部附属病院 伊藤明子 医師
メディアでも活躍中 西洋と東洋の医学に精通 今津嘉宏 医師
【大根&長ネギ 三番勝負】
① 栄養価
★大根のスゴいところ
カルシウムや鉄分は野菜でもトップクラス ビタミンCも旬の時期は豊富!
胃腸の働きをよくし、胃もたれ・胸焼け防止になるジアスターゼ、ガン予防、
動脈硬化予防、殺菌作用のあるイソチオシアネートが多くに含まれており、
アブラナ科の野菜を日常的に摂っていると食道ガンの発症リスクが約2/3まで抑えられる!
★長ネギのスゴいところ
ビタミンB1の吸収を促進、強力な殺菌効果があるアリシン、
インフルエンザウィルスの侵入・増加を抑えるフルクタン(青い部分に多く含まれる)、
テストステロン(男性ホルモン)を多く含まれており、テストステロンが多い人は
心筋梗塞のリスク5割減、ガンの死亡リスク3割減!
利き手の指の薬指が長い人はテストステロンが多い傾向がある。
② おススメ調理法
大根は葉の方がミネラルがより多く含まれているので、葉も捨てずに食した方がいい
長ネギは煮ることでフルクタンの吸収が効果的になる!
長ネギのアリシンは油で炒めることで減少を防げる
③ ㊙活用法
★メイプルシロップで作る大根アメ
抗酸化作用、抗菌作用、肝臓保護作用、ハチミツより血糖値の上昇がゆるやか
★長ネギみそ汁
ネギの硫化アリルという成分がワカメのカルシウムの吸収を妨げるのでネギとワカメはNG!
ネギと豆腐の組合せはどちらの食材もテストステロンを増やすのに効果的!
2016(平成28)年2月1日(月)午前の診療を休診させていただきます。
午後の診療は、午後3時から午後5時30分
家庭画報 2016年3月号(2016年2月1日発売)第59巻第3号「がん医療を支える人々」15 がんサバイバー530万人の時代を自分らしく生き抜く P.272~275 に、取材記事が掲載されました。