コラム



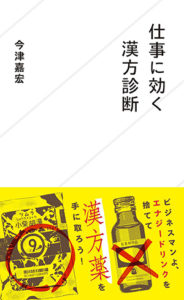
漢方薬は効かない。
これは私が医学生時代、大学病院のとある指導医から実際に言われた言葉である。
当時は西洋医学に軸足をおく者にとって、漢方薬はある種の未知の領域に存在する薬剤であったように思う。あえて誤解を恐れぬ表現をするならば"胡散臭い"と感じていた医師も少なくなかったのではなかろうか。
実際に私自身、西洋医学にその軸足をおく内科医であり、正直言って現場に出て漢方に触れるまでは、マニアの方がされているあまり客観的ではない治療といった印象を抱いていた。
このように私たち医師でさえ、やや懐疑的な視線を向けていたこの漢方薬。それを一般の多くの方々がどのように思われているか、おそらく想像に難くないと思う。
しかし近年、漢方薬に対する考え方や取り組みの見直しが進んできており、実際に医学生の教育カリキュラムにおいても、漢方の講義が取り入れられるようなってきている。これはつまり、以前より我々医師にとって、漢方が比較的身近なものになってきた証左であろう。
となればである、次の段階としては医療関係者以外の方にも漢方の有用性を知っていただき、日常で上手く接してもらうよう試みることはまさに自然な成り行きと言えよう。
だが残念ながら、ここに一つ大きな問題が存在する。
それは漢方の考え方は従来の西洋医学の考え方と異なる部分が多く、正直にいえば、医学生でさえ漢方の授業においてその考え方や用語の違いに戸惑うことが多いのである。
そのような漢方を一般の方々に伝えるためには、難しい漢方用語や医学用語が満載では決してならず、その上でわかりやすく平易に読め、かつ日常で気軽に役立つものでなければならない。
このような贅沢かつ難しい要求を満たす書籍が長年望まれていたわけだが、本書はそれらの要求を満たすまさにマスターピースの一冊となり得るのではないかと考える。
さて、そのような高い水準の要求を盛り込まれ、まさに漢方に触れる最初の一歩としておすすめできる本書であるが、そのタイトルは『仕事に効く漢方診断』。つまり日常生活を様々な仕事に埋め尽くされた現代人にとっては、まさにかゆいところに手が届くようなつくりとなっている。
それでは現代人が悩まされ、そして漢方が有効だとして本書にあげられている症状の一部をここに列記してみよう。
二日酔い、肩こり、便秘、疲労、風邪、冷え。
これらは本書内で取り上げられる症状の一部であるが、このいくつかはみなさんも経験したことがあるのではなかろうか。このような日常的に悩まされることがある症状に関して、それを少しでも軽減することができれば、誰しもの日常は今よりも少しばかり素敵で快適なものとなることは請け合いであろう。
では、果たしてそれは本当に漢方で可能となるのか?
ここで実際に、私の二日酔いに関する漢方体験をあげてみたいと思う。若いころは多少お酒を飲めるほうだった私であるが、最近は年齢を重ねるにつれ、年々お酒に弱くなりつつあるのを自覚している。そのため、最近では翌日が休みではない限り、あまりお酒は飲まないようにしているわけだが、中にはどうしても断れないケースというものも存在する。
その場合に取り出してくるのが、本書でも紹介されている黄連解毒湯。これさえ飲めばいくらでもガバガバ飲んで大丈夫......ということはないが、悪夢の二日酔いが軽減されるので、正直言って頭が上がらないお薬の一つである。
もちろん上記はあくまで私個人のケースではある。しかしサラリーマンの方でも、取引先や上司との酒の席では苦労されている方も少なくないと思う。そんな際に、少しでも翌日を有意義に過ごせる可能性があるなら、是非一度漢方を試してみるのも良いのではなかろうか。
もちろん二日酔い以外にも、先に記したように肩こりや便秘など慢性的な悩みになりうる症状に対して、漢方はその改善に寄与しうる可能性がある。だとすれば、このような様々な可能性を秘めた漢方という選択肢を、胡散臭いという理由だけで目を背けてしまうのは、あまりにもったいないと言えよう。
さて、本書の著者である今津嘉宏先生は、元々食道外科を専門とされておられ、完全に西洋医学に軸足をおかれていた医師である。しかしながら現在は、本書を執筆されたことからも伺えるように、漢方医学の可能性を伝える立場となられ、まさにその最前線に立たれている。これはやはり、西洋医学にはない漢方の有効性を体感されたことが、その理由とのことだ。
この西洋医学では効かない病気に対して、漢方が効果を示すというケース。これは臨床の現場において、決して珍しくはない光景である。実際に西洋薬が効かず悩んでいた時に、漢方薬を使うと嘘のように治ってしまったということも私自身しばしば経験したことがある。
ただし断っておきたいが、近代医学の発展において決して西洋医学を否定することはできない。何より私自身は完全に西洋医学に軸足をおく人間であり、当然のことながらその有用性と効果、そして着実な発展は日々実感するところである。
また漢方に関していえば、現代的な臨床研究の観点で見てみると、エビデンスと呼ばれる科学的根拠が弱いところが存在することは、残念ながら事実である。それ故に、漢方を第一選択にしているケースは正直いって決して多くはない。
しかしながら同時に、西洋医学的なアプローチでは、どうしても指の隙間から溢れてしまう病気や症状があることも、これまた覆しようのない事実なのである。
このような西洋医学では拾いあげることができぬ病気や症状は、当然のことながら昔の人々が経験してきたものも少なくない。となればである、まさにここにこそ、長い歴史で培われた漢方という先人の知恵を活かすことが良いのではなかろうか。
大事なことは西洋医学が上か、漢方医学が上かということではなく、日々を健やかに過ごすために役立つならば、迷わずどちらも適切に使えば良いという考え方であり精神であろうと私は考える。だからこそ、これまでいささか歴史の影に追いやられていた漢方医学を改めて見なおし、そして現代的に再評価することが今こそ必要とされているのであろう。
その意味において、これまで決して注目度が高いと言えなかった漢方医学に光を当てた本書は、仕事や生活を通して様々な悩みや病に晒される現代の我々にとって、日々の生活をより快活なものにしうるまさに必読の書と言えるのではなかろうかと私は考える。
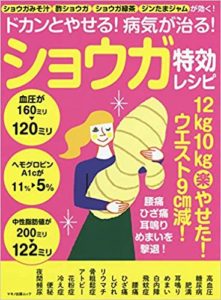
マキノ出版 2019年3月14日
★動脈硬化、糖尿病、高血圧など20以上の症状に効く!
日本の食卓にはなくてはならない食材「ショウガ」
ショウガには、血液を固まりにくくする作用、血流を増やす作用、動脈硬化を抑制する抗酸化作用などがあり、血管を若返らせてくれます。
また、食べることで血流が改善され、栄養のみならず、ホルモンや免疫細胞などを体の必要な場所に届けてくれるのです。
本書ではおいしく食べて健康になれる名医たちも太鼓判の5つのレシピを紹介!
そのレシピを食べて健康効果のあったかたたちの体験談も紹介しています。
万病の食薬「ショウガ」を食べて、お悩みの症状を一掃しましょう!
総論:ショウガの健康効果について
第1章:ショウガみそ汁
第2章:酢ショウガ
第3章:ショウガ緑茶
第4章:ジンたまジャム
第5章:ジンジャーエール
子供たちはもうすぐ春休み。短い休み期間が終わったら、4月からの新生活が待っています。新学期は朝から覚醒スイッチを入れて、毎日活動的に過ごしてほしいいものですが、中には起床後に体温が上がらず、通学意欲が低下している子供たちがいることが明らかに。“温朝食ラボ”は調査リリースの中で、1日のうちで最も体が冷える朝に身体を温めるために、温かいスープを飲むのがよいと提案しています。
中高生の男子を対象に、朝の通学意欲を調査したところ、「通学意欲なし」と意欲が低い生徒は、朝起きたときの体温が標準(36℃台)の場合15.9%だったのに対し、低体温傾向(36℃未満)の生徒では倍近くの29.6%に上るという結果に。
朝食の役割のひとつが、体温の上昇。低体温の生徒は、朝食を欠食しているか、朝食の内容が不十分な可能性があるとしています。
朝に身体を温める飲み物として「温かいスープ」と「温かいコーヒー」の2種類の飲み物で体温上昇の比較検証をした調査結果も発表されています。
検証は20代前半の女性2名、30~40代女性3名、50~60代女性3名の8名に対して実施。温かいスープと温かいコーヒーをそれぞれ摂取して、その後の体温上昇の変化をサーモグラフィで計測しました。
その結果、全世代で温かいスープの摂取直後から腹部・手の甲が温まって60分後も持続されていることが分かりました。一方、温かいコーヒーは摂取直後は多少温まるものの、その後の体温は低下傾向にあることが判明。
同じ温かい飲み物でも、スープの方が持続的に体を温めることが分かりました。調査を監修した芝大門 いまづクリニックの今津嘉宏院長はその理由として「スープに含まれる“とろみ”が大きく関係しており、とろみがあると、飲食物が胃の中に停滞する時間が長くなる」と指摘。「1日のうち体温が最も下がる朝だからこそ、温かいとろみのあるスープなど、体温を上げるものを意識的に摂り入れることが大切です。カロリーがあってお腹にたまるものを摂取しましょう」とコメントしています。

小学館 女性セブン 平成31年3月7日発行 第57巻第11号 P.72~76
7人の名医が教える最強の漢方薬8
がん専門医 おすすめ最強漢方薬
抗がん剤と併用でき、体力回復に効果的
「桂枝湯」

朝日新聞出版 週刊朝日 3月15日増大号 第124巻第5565号 P.32~33
小太りのほうが長生き 認知症リスクも低下「65歳からはデブがいい」
ぼっちょりさんには朗報だ。高齢者の肥満は認知症になりにくいという報告があったのだ。痩せすぎよりも小太りのほうが健康で長生きする。65歳以上のシニアはデブでいいのだ。
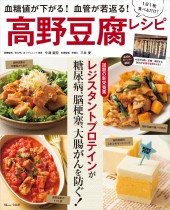
著者:今津嘉宏 医療監修/三井 愛 料理監修
発売日:2019年2月25日
価格:本体880円+税
日本古来の保存食品・高野豆腐が、血糖値を
下げ、血管を若返らせることで再注目!
高野豆腐はゆっくり凍らすことで
レジスタントプロテインを作り出します。
このレジスタントプロテインが糖の吸収を
おだやかにし、血糖値の上昇を抑えてくれます。
また、コレステロールを体外へ排出するため、
コレステロール値が下がるほか、
血管を若返らせ、血液がサラサラに。
究極の健康食材・高野豆腐を使った
絶品レシピ50品を収録!
もう治療の手立てがなくなった方、今受けている癌治療の苦痛を少しでも軽くしたい方、がんにこれから立ち向かおうとしている方、その悩みは様々です。中には数十年前に癌治療をお受けになったときの後遺症から逃れたいという方もいらっしゃいます。また、主治医に相談しても解決策がなかった、診察時は忙しそうで話す機会がない、診察の度に担当医が変わる、いくつかの診療科、医療機関にかかっているので総合的に診てもらいたい、など来院される理由は、ひとりひとり違います。
特に女性のがん患者さんは、乳癌や子宮癌、卵巣癌といった女性ホルモンに関係がある症状で苦労されている方です。年齢は20代から80代まで様々で、訴えも多岐にわたります。手術による後遺症、化学療法の副作用、ホルモン療法による体調の変化などにとどまらず、冷え症、肌の不調、脱毛、便通異常など、がんに関連しないと思われがちな体の不調も含めて相談に乗っています。
男性のがん患者さんは、働きながら治療を受けている方や糖尿病、高血圧症、高脂血症、痛風などの病気もお持ちで、がん治療を受けている方など、癌だけではなく、生活や経済的な悩みも抱えている場合が多いようです。クリニックでは、出社前に診察させていただけるように、朝の早い時間から診察をさせて頂いております。
「がん漢方」は、単に漢方薬を使った治療にとどまらず、漢方医学の眼をもって治療を行うことを意味しています。そこには漢方医学だけでなく、日本がん治療専門医機構 暫定教育医、認定医としてがん治療の専門医の眼から、日本外科学会専門医の眼から、さらに栄養医学を踏まえて、日本東洋医学会指導医、専門医として、「がん漢方」をすべてのがん患者さんに、おひとりおひとりを丁寧に診ることから、はじまります。

小学館 女性セブン 平成31年2月14日発行 第57巻第8号 P.146~151
目からウロコの予防術26 風邪にもインフルエンザにも負けない体は、作れる!
”ちょい足し”で免疫力アップ!
ワザ1 朝イチの白湯で体温を一気に上げる
ワザ2 決まった時間に起きて体内時計を整える
ワザ3 爪もみで体の末端から効率よく血行アップ
ワザ4 野菜は色が濃いもの、肉は赤いものを選ぶ
ワザ5 腸の血流を良くして免疫細胞を活性化
ワザ6 天然素材の下着で汗をコントロール
ワザ7 時間がないときは効率よく温める湯船シャワー
ワザ8 筋力をつけて冷えない体づくり
ワザ9 仕事の合間に深呼吸をして血流UP
ワザ10 布団はかけ布団の上にかけるのが正解
この度、「温朝食ラボ」は、受験シーズンが本格化するタイミングにて、全国に住む受験生の男女200名を対象に、冷えと朝食に関する調査を実施いたしました。
調査結果から、受験生の7割以上が冷えと戦いながら勉強している実態が浮き彫りとなり、さらに冷えの影響で4割以上が集中力の低下に繋がっているという問題も明らかになりました。一方で、朝食の欠食率が問題視される中、毎日朝食を摂っている人が8割以上という結果となり、普段の食事として約7割が「温朝食」を積極的に取り入れている実態が分かりました。
そんな中、受験生にとって大切な受験当日の朝ごはんとして、ゲン担ぎとなる食事ではなく、8割以上が「温朝食(温かいスープとパン)(お味噌汁とご飯)」を希望していることも判明しました。下記にて、詳細についてご報告いたします。
■主な調査結果TOPICS
朝食摂取に関する質問をしたところ、全体の8割以上(84.5%)が「毎日」と回答し、「朝食は摂らない」と答えた人は6.0%となりました。近年、朝食の欠食率の高さが問題視される中、受験生にとっては毎朝の活力となる朝食は積極的に摂取している傾向が伺えます。また、普段の朝食として、6割以上が『温朝食』を積極的に摂っている実態も明らかになりました。
<普段どのくらいの頻度で朝食を摂っていますか(SA)>
<温朝食と冷朝食、どちらを摂ることが多いですか(SA)>
グラフ2
勉強中や試験中に身体が冷えることがあるかと質問したところ、全体の7割以上(74.5%)が冷えを感じながら勉強に励んでいる実態が明らかになりました。さらに、冷えによって生じる不調について聞いたところ、最も多かったのが“集中力が切れる”と“お腹が痛くなる”という回答が同率で最も高く、受験において冷えという課題が勉強に影響を与えていることが示唆されました。
<勉強中や試験中に身体が冷えることはありますか(SA)>
冷えを感じている人 74.5%
<冷えが原因で生じる不調があれば教えてください(MA)>
受験生が寒さを解消するためによく飲むものを聞いたところ、1位は「お茶(46.5%)」となり次いで2位は「スープ(31.0%)」という結果になりました。3位に紅茶、4位にコーヒーと続いており、受験生にとって寒さを解消しつつ小腹も満たすスープを重宝していることが伺えます。温朝食ラボではスープを飲み、身体を芯から温めることで体温を長時間保てるという可視化実験も行っており、受験生にとってスープは受験を助けるサポート食として推奨いたします。
<受験勉強中、寒さを感じたときによく飲むものを教えてください(MA)>
受験生にとって大切な受験当日の朝に食べたいものを聞いたところ、“温かいスープとパン”や“お味噌汁とごはん”といった『温朝食』を希望している人が8割以上(83.5%)という結果となりました。ゲン担ぎをした食事など話題になりますが、やはり受験生にとっては日ごろから食べなれている『温朝食』で大切な1日をスタートさせることで、朝から脳を活性したいという気持ちが伺えました。
<受験当日の朝に食べたいものを教えてください(SA)>
温朝食を希望 83.5%
冬場の体調や様子について聞いたところ、全体の約9割(86.5%)が何らか冷えに通じる冬場の不調に悩まされている実態が明らかになりました。手や足、腰など全身への冷えを感じている人が多くいることからも受験生にとって冷えは天敵であることが伺えます。また、今津先生によると1つでも項目が当てはまることで冷え症の疑いがあり、寒さを感じた際には温かいスープを飲むなど対策をすることをお薦めします。
<冬場の体調や様子について、当てはまるものをすべてお選びください(SA)>
■調査概要
目的 :受験生における「冷えと朝食」についての実態を明らかにする
方法 :インターネット調査(調査委託:クロスマーケティング)
対象 :全国の受験生 200名
調査期間:2018年12月19日~12月21日